 業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 事務所所長 マンション管理士 重松秀士が、マンション管理 コンサルタントならではのお役立ち情報をお届けします。 携帯版
業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 事務所所長 マンション管理士 重松秀士が、マンション管理 コンサルタントならではのお役立ち情報をお届けします。 携帯版
前回に続き、給排水管更新工事に関してご紹介致しますが、今回は、実際のスケジュールに沿って、設計事務所作成の図面及び仕様書を基にした施工会社の募集・選定作業の部分から、各工程の具体的な内容とポイントをご説明致します。
なお、記事中で特に明記致しませんが、重松マンション管理士事務所は本工事のコンサルタントとして修繕委員会の立上げ後、長期修繕計画の全面見直しや修繕積立金の改定から関わり、工事完了までサポートさせて頂いております。
- 目次
0.給排水管更新工事のスケジュール
| 年月 | 内容 |
|---|---|
| 平成24年12月 | 設計概要説明会 |
| 平成25年1月 | 施工会社募集広告掲載 |
| 平成25年4月 | 施工会社内定 |
| 平成25年5月 | 通常総会で施工会社承認 |
| 平成25年6月 | 工事概要説明会、工事着工、共通仮設工事開始 |
| 平成25年8月 | 事前調査、室内工事テスト施工及び共用部分の給水管更新工事 |
| 平成25年8月〜9月 | 室内工事説明会 |
| 平成25年9月 | 室内工事開始 |
| 平成25年12月 | 室内工事終了、共通仮設撤去 |
| 平成26年1月 | 竣工図書引き渡し |
1.工事業者の選定と管理規約の改正
設計概要説明会は驚異の出席率92%!
 このマンションでは、工事実施予定の3年程前に給排水管改修工事に向けた修繕委員会を立ち上げ、工事実施の必要性等について調査と検討を重ねると共に、折に触れ、漏水事故発生の事実や委員会の活動状況を広報紙で住民に知らせてきました。
このマンションでは、工事実施予定の3年程前に給排水管改修工事に向けた修繕委員会を立ち上げ、工事実施の必要性等について調査と検討を重ねると共に、折に触れ、漏水事故発生の事実や委員会の活動状況を広報紙で住民に知らせてきました。
その甲斐もあって、平成24年12月初めに2日間開催した「設計概要説明会(工事の必要性や工事内容のあらましを説明するためのもの)」は、全約300戸の92%が出席するという驚異的な数の住民参加を得て大成功のうちに実施出来ました。一般的な管理組合の総会の出席率が10〜30%程度であることはご覧の皆さんがよくご存知だと思いますが、それと比較すれば92%という数字がいかにすごいことかご理解頂けると思います。
施工会社の公募〜修繕委員会による選定作業
「設計概要説明会」の大成功を受けて、早速、修繕委員会では施工会社募集要項の検討に着手しました。
そして、昨年(平成25年)1月中旬に業界紙に施工会社募集広告を掲載し、以降、第一次・第二次・第三次の各選考手続きを経て4月中旬に施工会社1社を内定する運びとなりましたが、この間の手順及び留意点等は外壁や屋上防水等を実施する一般の大規模修繕工事(以下「大規模修繕工事」といいます。)の場合とほぼ同じであるため、説明を省略します。
通常総会を経て施工会社を決定〜着工へ
内定した施工会社には管理組合から内定通知を送ると共に工事の進め方等について非公式の打合せを行い、工事実施に向けた準備を進めて貰うことにしました。
そして、5月下旬開催の通常総会に、『専有部分の工事費用を修繕積立金から支出することができるようにするための管理規約の一部変更案』及び『工事発注先・発注金額・工事予備費等の一括承認案』を上程し、審議したところ、いずれも満場一致で承認されたため、いよいよ6月の着工に向けて動き出すことになりました。
専有部分も修繕積立金で工事をするため、管理規約を改正
専有部分である横引管の工事費用を修繕積立金から支出することについては、いろいろと議論があるところですが、個人負担で実施することにすると、改修が進まず、結局は漏水事故が多発するようになってしまいます。個人の費用負担なしに実施できるなら反対する人はあまりいませんので、管理規約を改正せずに総会決議だけで進めてしまう場合もありますが、重松事務所のアドバイスもあり、この管理組合では、きちんと管理規約を改正して対応することにしました。
※追記1:2017年9月、最高裁により「マンション管理組合が大規模修繕工事等の修繕を実施する場合、一定の条件のもとで修繕積立金を専有部分の工事に使用することは、違法ではない。」という趣旨の判決が出ました。詳しくは「修繕積立金を専有部分の改修に使用した事例の最高裁決定について」をご参照ください
※追記2:2021年6月に改正されたマンション標準管理規約では、配管についてコメントが追加されています。詳しくは「マンション標準管理規約が改正され、配管工事についてコメントが追加されました」をご参照ください
2.工事概要説明会の開催
工事開始に当たりまず一番初めに行うことは、施工会社による「工事概要説明会」の開催です。
ポイント具体的でわかりやすい資料づくり
そのため、施工会社が作成した素案を基に修繕委員会及び当事務所で3回に亘り修正作業を行いましたが、その結果出来上がった完成版は非常に見やすく解りやすい物になりました。
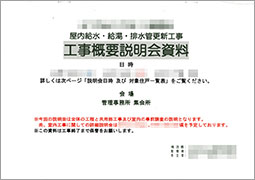
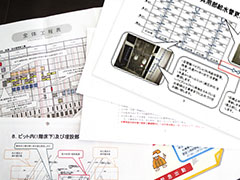
ポイント参加しやすい日程を用意する
 また、当然今回も多数の住民に参加をして貰う必要があることから、住民が参加しやすいように配慮する必要があります。先の通常総会終了直後に開催案内を全戸配布すると共に出席票の回収を促進した結果、今回も出席率86%という極めて大勢の住民の参加が得られました。
また、当然今回も多数の住民に参加をして貰う必要があることから、住民が参加しやすいように配慮する必要があります。先の通常総会終了直後に開催案内を全戸配布すると共に出席票の回収を促進した結果、今回も出席率86%という極めて大勢の住民の参加が得られました。それでは、その資料及び説明会の内容に基づいて、今回の工事の概要をご説明します。
3.共通仮設工事と共用部分の給水管更新工事
共通仮設工事
 工事概要説明会終了後直ちに「共通仮設工事」が行われます。
工事概要説明会終了後直ちに「共通仮設工事」が行われます。
これは、現場事務所・作業員詰所・資材置場・材料加工場・作業員用仮設トイレ・手洗い場・工事用掲示板・工事用ポスト・居住者用仮設トイレ等の各設置を行うものですが、今回の給排水管更新工事は作業員が住戸内に立入って作業を行うため住人が自宅のトイレを使用しにくい場合があることや、丸1日の断水が1度、短時間の断水が2度それぞれ発生するためトイレを使用できない日時があることから、居住者用仮設トイレを敷地内に設置することがその特徴です。
共用部分の給水管更新工事
共通仮設工事が終了しますと、早速「共用部分の給水管更新工事」が約2ヶ月間に亘って行われることになります(300戸を超える大型団地であるため、これだけでも2ヶ月かかります)。
これは、各棟の1階床下ピット内と各階パイプシャフト内の給水管をそれぞれ新品に交換する工事ですが、既存の給水管が一時的に使用できなくなることから仮設の給水管を各住戸に設置してから工事を行うことがこの工事の特徴です。
4.全戸室内事前調査と室内工事テスト施工
上記の共用部分の給水管更新工事と並行して、全戸室内事前調査及び修繕委員宅数軒を対象とした室内工事テスト施工が行われます。
実は、この二つが今回の工事の命運を左右することにもなる極めて重要な手続きになります。
全戸室内事前調査
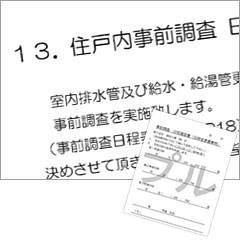 まず、「全戸室内事前調査」ですが、これは今回の工事を計画通り進めるために予め各戸の室内調査を行い、室内工事内容の説明や工事日当日の在宅確認、浴室・洗面所・トイレ・台所・給湯器・物入れ等についてリフォームの有無や各器具の形状、天井・床の内装材の各確認をします。
まず、「全戸室内事前調査」ですが、これは今回の工事を計画通り進めるために予め各戸の室内調査を行い、室内工事内容の説明や工事日当日の在宅確認、浴室・洗面所・トイレ・台所・給湯器・物入れ等についてリフォームの有無や各器具の形状、天井・床の内装材の各確認をします。
しかし、これが実は非常に難問なのです!
と言いますのは、この事前調査を行うためには、300戸を超える全住戸を対象に施工会社の人が一軒ずつ訪問して室内に立入ることになりますが、当然、その調査日時にはその家の人に在宅していて貰う必要があります。この日程合わせが難しいのです。
 この団地の場合、事前調査に約2ヶ月間を要することになっているのですが、工事概要説明会の資料中に施工会社が予め作成した各住戸の「事前調査日程表」が掲載されており、各戸にその都合の可否を専用用紙(「事前調査日程確認書(日時変更申込書兼用)」)にて調査予定日の1週間前までに届け出て貰うことにしました。
この団地の場合、事前調査に約2ヶ月間を要することになっているのですが、工事概要説明会の資料中に施工会社が予め作成した各住戸の「事前調査日程表」が掲載されており、各戸にその都合の可否を専用用紙(「事前調査日程確認書(日時変更申込書兼用)」)にて調査予定日の1週間前までに届け出て貰うことにしました。
ところが、指定日時では都合が悪いため本来なら日時の変更申込みをしなければいけない人だけでなく、都合のよい人も含めてこの日程確認書を期限までに提出しない住戸があるのです。
そうなると"1週間前"という期限を過ぎた時点で戸別訪問をしたり電話をしたりして確認をしなければなりません。また、日程確認書を提出した人であっても、その日時に訪問してみると在宅しておらず、すっぽかされてしまう住戸もあるのです。そうなると、また連絡を取って調査日時を決め直さなければならないなど、大規模修繕工事の場合とは全く異なる手間と苦労が室内工事には存在するのです。
これがひとつ目の大きな関門です。
室内工事テスト施工
次に「室内工事テスト施工」のことですが、選出した数戸に対してリフォーム状況も踏まえて今回行う工事と全く同一内容の工事を試験的に行い、施工上の問題点を探ろうというものです。
このテスト施工の結果により、当初考えていた材料や施工方法、施工順序を一部変更することもあるなど、これまた今回の工事を成功させるための大きな鍵になります。
ポイント各戸の個別事情に合わせたきめ細かい対応を協議する
そこで洗い出される戸別の特徴とは例えば次のようなものです。
- 給水給湯管を既に更新済み、または一部更新済みという申告あり
- 配管工事終了後にリフォームを予定しているので、内装の仕上げは不要
- 風呂をユニットバスに交換済みの場合、その脱着の可否
※ユニットバスの場合、天井・壁・床を脱着出来れば配管をその裏側に隠すことが出来るため、配管が目に見えなくなる"隠蔽工法"を採用することが出来る - 浴室や台所のタイルが剥がれそうである
- 台所の床がフローリング上にCF(クッションフロア)またはフロアータイルが貼られている。
※今回、管理組合では、フローリング仕上げを標準仕様としたため、表面に貼られている部材の取扱いが問題になる - 給水給湯の露出配管部に棚板や吊り戸棚等の障害物があるため、貫通工事を要する
- 廊下物入れの建具が天井まであるため、建具加工が必要
- ガスコンベックの脱着が必要 等々
こんな点も大規模修繕工事とは全く様相が異なるところです。
5.室内工事説明会
以上の経過を経て、いよいよ今回の工事の主題である室内工事に着手することになりますが、先ずはその冒頭で例によって住民説明会を開催します。
住民にとって最も身近な内容を説明する場
説明会は既に2回行っていますが、今度の「室内工事説明会」が住民には最も身近で切実な内容になりますので、今回もその資料の内容には細心の注意を払いました。
そして、今回も出席率85%という非常に多数の住民参加を得ました。
6.各戸室内工事
第2の関門は、室内工事日程
室内工事を始める前に、当然各戸に具体的な日程を知らせるわけですが、実は、この工事日程確定版はとりわけ重要なものであり、円滑に工事を進めるためのふたつ目の大きな関門です。
その理由は、排水管の竪管は1階から5階の全住戸内を一本の配管が縦に貫通しているため、この竪管を更新する場合には1階から5階まで同時に工事を行うことになります。そのため、排水管更新工事の日には縦系列の全戸が在宅している必要があり、たとえ1戸でも不在のため入室出来ない住戸があると、5戸全部の工事が出来ないことになってしまうからです。
また、工事日当日に不在になることが判っている場合は、必ず事前に施工会社の責任者に相談をして貰うことを徹底しました。
それでは、当日の資料及び説明内容に沿って、室内工事の概要をご説明していきます。
工事内容
1 浴室・洗面・洗濯系統の排水管(竪管及び横引き管)の更新工事
台所とトイレの排水管はまだ交換時期ではないため、今回は更新しません。
そして、これらの工事期間中に丸1日の排水禁止が発生します。


2 水道メーターから衛生器具接続部までの給水・給湯管の更新工事
これらの工事期間中に丸1日の断水が発生します。
なお、上記「1」「2」に共通することですが、これらの工事に伴い、流し台・洗濯機・洗面化粧台の脱着や対象箇所の天井・床の解体・復旧・仕上げ工事を行うことになります。
▼廊下の壁・天井・クローゼットを解体している様子



工事工程
次に工程ですが、次のとおり1戸につき5日間の入室作業を行うため、全戸の工事を完了するには3ヶ月近くかかることになります。
| 1日目 | 天井・床の解体及びコンクリート削り |
|---|---|
| 2日目 | 排水管の更新 |
| 3日目 | 給水・給湯管の更新 |
| 4日目 | 天井・床の内装下地復旧 |
| 5日目 | 天井・床の内装仕上げ |
工事手順
全戸の室内工事を計画通り行うためには、その手順等が非常に重要です。
1 室内工事日程を知らせる
まず初めに、確定した「室内工事日程表」により全戸に亘って住戸ごとの具体的な室内工事日程を知らせます。
2 工事内容の周知徹底
室内工事5日間の工事日程は前述の通りですが、更に1日ごとの詳しい作業内容、台所・洗面所・洗濯機・トイレ・浴室の使用可否状況、図と写真による解体復旧範囲などをそれぞれ周知します。
3 仕上げ材選定申込書の準備
天井と床を解体することから、復旧仕上げを行うにあたり仕上げ材をどうするかという問題が出てきます。
今回、管理組合では、原則として各戸解体時の既存材料に合わせて復旧することにしましたが、一部(浴室天井その他)は仕上げ材を統一的に指定すると共に、一部(洗面所天井)については、予め標準仕様の材料見本を10種類ほど選んで集会所に展示しておき、その中から好みの物を各戸に選んで貰うという方法を採用しました。
4 配管方法の意向確認
ユニットバス以外の在来型浴室の場合は、構造上、配管が隠蔽出来ず露出工事になってしまうため、その配管の仕方について3種類の工法を紹介して各戸の希望を取ることにしました。
5 室内の片付け要請
更に重要なこととして、住民には予め工事対象箇所の家具や小物の片付けをしておいて貰う必要があるため、片付け範囲を図と写真で細かく説明し、片づけを強く要請しました。
また、要請するだけでなく支援体制も作りました。こういうところも室内工事ならではの特徴的な点です。
6 緊急連絡体制など

▲緊急連絡体制夜間・休日に漏水事故等が発生したときのため、施工会社の緊急連絡体制もきちんと整えて貰いました。
また、室内工事期間中は傷防止や汚れ防止のため床に3層の養生シートが敷かれたままになりますが、一番上のシートについては毎日取り替えるなど細かい配慮もなされています。
本当は一つ一つもっと詳しくご紹介したいところですが、大まかなところはご理解頂けるのではないかと思います。
文字だけで見ると簡単そうに見えますが、なにせ300戸を超す団地型マンションの全戸が対象になるため、実際のこれらの対応には私も含めて非常に気を遣いました。
7.工事完了後
9月中旬に始まった室内工事も、住民の皆さんの協力と修繕委員会の精力的な活動及び理事会の支援を得て、12月上旬に無事に全戸の工事が完了しました。
思えば、今回の工事を行うためにワーキンググループ及び修繕委員会を組織して以来、3年半の年月を経て漸く目的が達成されたことになります。
そして、室内工事完了後は、共用給水管の保温工事の残りや雑補修工事、工事後アンケート対応、現場事務所等の共通仮設撤去等が行われ、遂にクリスマスの翌日に全てが完全に終了致しました。
7ヶ月間に亘ったあの喧騒が、今はまるで嘘のような静けさです。
あとは、施工会社に竣工図書を作成して貰い、1月末に引き渡しを受けるだけです。
8.まとめ
以上、室内工事主体の給排水管改修工事の特徴を説明させて頂きましたが、屋上防水・外壁塗装・鉄部塗装等を中心とした大規模修繕工事とはその様相が大きく異なることがお解り頂けたことと思います。
給排水管更新工事の重要なポイントは前回の記事でご紹介させて頂きましたが、大切なことですので、もう一度それぞれを補足しながらまとめさせて頂きます。
1工事を成功に導く「2つの会議」〜定例会議と修繕委員会
大規模修繕工事にしても給排水管改修工事にしても、工事を行う場合は一般的に「修繕委員会」を組織し、工事方針や基本計画を始めとした諸々の事項について検討を行った上で実施に踏み切るものですが、工事が始まってからはそれと並行して、施工会社・建築設計事務所の2者、又はそれに管理組合・マンション管理士が加わっての3者、4者の「定例会議」というものを開きます。
実は、この定例会議の役割は非常に重要なものであり、工事を進めるにあたって日々起こる色々な問題について全員でその状況を把握すると共に、判断を要するものについてはその都度迅速に決断をしていくという機関になります。
そして、4者定例会議で日々起こる細かいことについて迅速に対応を行うと共に、修繕委員会には定例会議の内容を報告し、重要事項について判断・決議を行うという形で進めてきました。
今回の工事が順調に推移したのも、この2つの会議があったからこそです。
2不公平をなくし、円滑に進めるための「きめ細かい配慮と準備」
くり返しになりますが、全戸の室内に立入って工事を行うことになるため、きめ細かい配慮や準備が必要になります。
そのために、室内工事を行うにあたり想定される種々の状況・現象について、予め管理組合としてその対応方法を決めておくことが必要になります。
なぜなら、問題が起きた時に場当たり的な対応になってしまい、結果として住民間に不公平・不公正な状態が発生してしまうことにもなるからです。
- 内装材を管理組合の指定した標準品よりも上質の物を使用したい
- 工事期間中に在宅出来ない
- 鍵を預けて貰えなかったり、事前連絡もなく突然不在になったりして、予定日に施工できない
- 工事実施に非協力的なため、他住戸に支障が発生してしまう
今回の場合は、工事開始の1年近く前からこれらの検討に入り、その後施工会社から提出された「室内工事に関わる事項確認書」も踏まえ、全部で40〜50項目について一つ一つその取扱いを協議しました。
こうしたことも今回の工事が混乱なく終了した大きな理由だと言えます。
3何としても必要な「努力と誠実さ」
もうひとつ大切なのは、室内に立入って行う工事の性格上、いかにして住民の理解や協力を得るか、ということです。
住民に工事の意義を理解して貰い、管理組合や施工会社から依頼・指示されたこと(例えば、事前調査時及び工事実施時の在宅、家具類の片付け、排水禁止など)はきちんと実行して貰うといった協力がないと工事は円滑に実施できません。
そのためには、住民への広報や説明といった活動を丁寧に、かつ繰り返し行うと共に、それらに関する住民からの疑問や不安、質問に対して丁寧に答え、納得して貰うための努力と誠実さが理事会・修繕委員会側には何としても必要です。
このことも、工事を成功させる重要な点です。
現に、この団地の近隣2団地でも近年同様の工事が行われたそうですが、両団地とも何軒かの工事未実施(拒否宅を含む。)が出たということであり、300戸を超す当団地で一軒の未実施住戸が出なかったということに大きな驚きを持っていたようです。
◇
2回に渡る記事の中では、大規模修繕工事と似ている部分を割愛し、給排水管更新工事ならではの部分、特にプロセスを中心にご紹介してきました。
しかし、実際にはそれ以外に大規模修繕工事と同様に、予算の問題や設計事務所や施工会社の選定作業等があり、そのあたりの負担や注意点は同じようにあります。
重松マンション管理士事務所では、そうした初期段階から工事完了までをコンサルティング・サポートさせて頂きましたが、今回の工事が安価で良質かつ極めて順調・円滑に終わり、1月に執り行われた工事竣工セレモニーでは理事長から感謝状をいただいたことを最後に補足し、終わりとさせて頂きます。
よろしければ、こちらもご覧ください。
▼給排水管全面更新工事コンサルティングのお客様インタビュー
当団地初の給排水管更新工事は2年に及び、とにかく大変で(笑)家内からは「いい加減に」と・・・
<参考>給水管・排水管関連工事の記事
マンション管理コンサルタント マンション管理士 重松 秀士(プロフィール| )
)
資料請求 無料相談・お問い合わせ マンション管理士事務所
最近追加されたお知らせ&日記(ブログ)10件
お問い合わせはこちらから。安心してご相談下さい!
マンション管理一筋! 業界トップクラスの実績、充実の設備と支援体制が自慢の重松マンション管理士事務所の詳しい業務については、マンション管理士事務所HPをご覧下さい。
「マンション管理相談」「顧問契約(管理組合顧問)」「大規模修繕工事コンサルティング」「建物診断・長期修繕計画作成のサポート」「管理規約の改正」「管理費削減」「管理会社変更」「管理費滞納」「理事長代行」「マンション自主管理サポート」「簡易ホームページ作成・運営支援」など、各業務に関する詳細の内容や各業務の「資料請求」、「スタッフ紹介」や「お客様インタビュー」などをご用意しています。







コメント
▼コメント投稿フォーム
※可能な限り頂戴したコメントには返信するように努めておりますが、必ずしも返信できる訳ではありませんこと、あらかじめご理解の上ご投稿ください。
※無料相談をご希望の方は、お問い合わせフォームからお願いいたします。